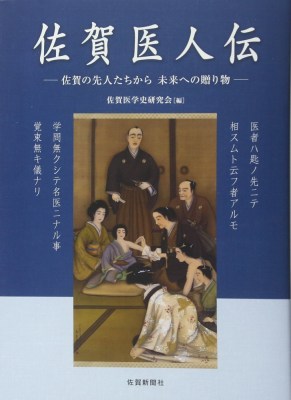精神医療時代の芸術のために: 「精神医療と音楽の歴史」講演会参加記 /坂本 葵
アドルフ・ヴェルフリ(Adolf Wölfli, 1864-1930)という、世界的に有名なアール・ブリュットの芸術家がいる。統合失調症の診断を受けてから生涯を精神病院で過ごしたヴェルフリは、病室で奇想天外な絵を描き始め、独自の形態語彙でノートを埋め尽くし、詩を書き作曲に没頭し膨大な作品群を残した。さて今年の春、ヴェルフリの本邦初の本格的回顧展である「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」展を東京ステーションギャラリーで観ながらふと実感したのは、その緻密で学究的な展示構成といい、会場を満たす観客の冷静な雰囲気といい、いわゆる「狂気の異端芸術家」がセンセーショナルに喧伝され消費されるような時代は、もはや過去のものになったということだった。
そもそも、1945年ジャン・デュビュッフェ(Jean Philippe Arthur Dubuffet, 1901-1985)によって提唱された「アール・ブリュット」(主に精神障害者の芸術作品を指す)、それを1972年にロジャー カーディナル(Roger Cardinal, 1940-)が拡張した「アウトサイダー・アート」という概念は、現代においてその有効性が問い直されるべき時期に来ている。権威ある正規のアカデミーで芸術教育を受けなければ美術家や音楽家になることが不可能だった時代とは異なり、現代では誰もがアーティストになりうる。無名の若者が動画投稿サイトに自作の映像作品をアップし、世界中から何百万というアクセスを得て成功することも夢ではないのだ。
こうした時代において、芸術教育を受けていない人や精神疾患の芸術家を「アウトサイダー」として線引きすることに果たしてどれほどの意味があるのか、疑問視されてしかるべきである。そうしたアウトサイダー・アートが権威ある芸術へのカウンターとなり革命につながるという期待についても、現代においては時代錯誤の感が否めない。
だから私たちが今すべきことは、「狂気の芸術家」をアウトサイダーという枠の中に囲い込んで無批判に特別視することではないはずだ。そうではなく、もし何らかの芸術が精神医療という文脈と不可分の関係にあるのならば、その両者の関係を明らかにしていくことこそ有意義であると考える。例えば美術史家が、画家の師弟・交友関係やモデルについて調査したり、アトリエの変遷と作風への影響を分析するのと同様に、芸術が生まれ享受される場として、精神病院や精神医療の歴史は研究されてもよいかもしれない。
本講演「精神医療と音楽の歴史」は、芸術における精神疾患の表象、芸術療法の歴史といったテーマを基に講演とコンサートを組み合わせ、歴史上の精神医療と音楽の関係を探求するという、意欲的で革新的なプロジェクトである。9月9日に行われた二つの講演は、精神医療と音楽に関する議論に先立って、西洋と日本それぞれにおける精神医療の歴史を基礎的に概観したものであった。
 |
 |
「精神医療と音楽の歴史」 2017年9月16日(土) ‐終了‐
高林 陽展氏「西洋世界における精神医療の歴史」では、古代から現代に至るまで西洋世界で精神疾患がどう理解されてきたかが示された。
古代における狂気は、天が人間に与えた宿命や神罰と考えられ、神の超自然的な偉大さに翻弄される人間の無力さを象徴するものだった。その中で医学的見地から精神病を説明したのは、「四体液説」に基づき、躁状態は黄胆汁の、鬱状態は黒胆汁の過剰によって引き起こされる症状だとしたヒポクラテスらの医学である。中世においても、狂気は悪魔の憑依や信仰上の苦悩によってもたらされるという超自然的な解釈が一般的であった。
科学革命以後の啓蒙の時代になると、狂気の原因が身体や脳の不調によるものと説明されるようになり、治療の対象とみなされるようになる。そして18世紀以降、それまで家庭や修道院などで私的にケアされてきた患者たちを専門の施設、つまり病院に隔離収容するという動きが現れ「精神病院の時代」が始まる。19世紀になると公立精神病院が数多く作られるようになり、患者数も飛躍的に増加した。つまりこの時代に確立された狂気のイメージは精神病院と不可分であり、狂人とは病院に閉じ込められ社会的に疎外された存在である、という見方が一般的になった。本稿の冒頭で述べた「アール・ブリュット」概念も、まさにこのような狂気・狂人のイメージに基づいた発想であると言えよう。
1950年代以降になると、薬物療法の発展に伴い脱施設化と地域精神医療化が進行した。そうして「精神病院の時代」から「精神医療の時代」へと移り変わったのが現代である。

鈴木 晃仁 (慶應義塾大学)の講演の様子。多くの参加者が熱心に耳を傾けた。
鈴木 晃仁氏「日本における精神医療の歴史」では、近世から近現代までが射程とされた。近世医学において、精神疾患は「気」の病としてとらえられていた。精神医療のあり方としては、幕府や藩の命令による公式の監禁と非公式の管理があったが、いずれにしても患者を監督し世話を担うのは家族であった。また、「乱心」のような精神疾患だけでなく放蕩や不良などの行為に耽る者も、「家」を乱す者として同じく監禁の対象としていたことなどが指摘された。
近代化に伴い、日本の精神医療は欧米に倣った精神病院システムの導入と、近世の流れを踏襲した私宅監置という二つの流れで進んでゆくが、明治から昭和にかけて精神病院が緩やかに増加してゆくのに対し、私宅監置は次第に病院に取って替わられるようになる。
「狂気」は前近代の能や歌舞伎などでも重要な要素であるが、その芸術的伝統を引き継ぎつつ、近代文学では精神疾患や精神病院が欠くべからざるモチーフとなった。
病院はまた、患者自身の言葉や表現をカルテや聞き取りなど記録の形で残し、それを大量に蓄積するアーカイブズの機能も担っている。これらのアーカイブズを医学的視点だけでなく様々な見地から研究し、その成果を社会へ還元していくことが必要だ、という提言で本講演はまとめられた。
高林氏の講演でもギルマンの説を引いて指摘されていたように、私たちは病への恐れから正常と異常の境界線をどこかに引き、狂気を懸命に「他者化」しようとする。したがって精神疾患が社会でどのようにとらえられてきたかについて歴史的変遷をたどることは、いいかえれば、境界線がその都度どこで引かれてきたかを知ることであり、私たち人間が生きる上で何を恐れてきたのかの歴史を知ることでもあるのだろう。
坂本 葵(さかもと・あおい)

1983年生まれ、作家。
『食魔 谷崎潤一郎』(新潮新書、2016)では、谷崎潤一郎の作品と生涯を「食」の観点から読み解いた。現在は谷崎文学における身体論に関心があり、皮膚と衣装、アンドロイド、老いと病などの主題で考察している。