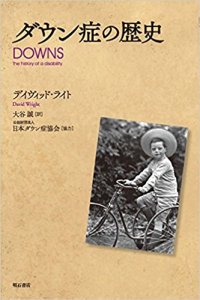『病は気から』を病院で読む /鈴木 晃仁(慶應義塾大学)
SPAC静岡県舞台芸術センター(Shizuoka Performing Arts Center)が、モリエール原作の戯曲『病は気から』を2017年の10月に上演する。その台本を病院で読み合わせる「リーディング・カフェ」に参加した。6月29日の夕刻7時から9時半くらいまで、場所は静岡市の浜本整形外科医院の待合室。
SPACは静岡県が設立した劇団であり、創造的な舞台芸術活動を地元に根付かせながら、世界的な視点を持っている。日本ではなかなか見られない地方自治と芸術の関係をキープしている。1995年の設立時の初代の芸術総監督は鈴木 忠志であり、2007年からは宮城 聰が二代目の芸術総監督をつとめている。静岡はもちろん、国際的な演劇祭などでも活躍しており、地元の人々に深く愛されている。
「リーディング・カフェ」というのは、SPAC俳優の奥野 晃士いわく、(おそらく)彼が考えついたアイデアとのこと。俳優たちが一緒に台本を読む「読み合わせ」と同じように、一般参加者が和気あいあいと楽しく台本を読むのである。2008年から400回ほど行っている。今回のリーディング・カフェも楽しくて、読み方を間違えたり、難しい外国人の名前(「ディアフォワリュスさん」)がすらすらと読めなくても、怒った演出家にタバコの灰皿を投げつけられるようなことはない(笑)。
今回の企画の特に面白いところは、本物の病院で、医療にかかわる芝居の読み合わせをするところである。参加者の一人は「洒落がわかる」企画だと感心していた。モリエールの『病は気からLe Malade imaginaire 』は、1673年2月にパリで初演された作品。主演俳優はモリエールその人だったが、公演中に病で死亡するというダークなエピソードもついている。本作で特に重要なことは、当時の医師や患者を嘲笑した点である。医師たちはギリシア語とラテン語のテキストを読み解くばかりで、現実の病気や治療にはまったく疎い愚かな人々である。患者はさらに愚かで、医者たちに言われるがままに自分を病気だと思い込み、治療を受け、養生をして、薬を買い、浣腸をされている。医者を尊敬するあまり、医者の息子に自分の娘を嫁がせようとしている。そんな愚かな医者と愚かな患者が作る状況の中で、患者の弟と女中が一計を講じ、最後には娘と彼女の恋人が勝利する喜劇を描いたのが『病は気から』である。医療をたたえたり、患者に共感したりする定番ストーリーの真逆のシナリオである。
ところが、意外なことに、この作品の読み合わせに集まり楽しんでいた参加者の多くは医療関係者であった。参加者は男6名、女14名の計20名。SPACが培ってきた静岡の演劇や舞台の愛好者と、リーディング・カフェの場所を提供した浜本医院が軸になって作る医療関係者の二つの系列があった。そして面白いことに、この二つのグループは重なっていた。浜本医院に勤務する医師で、趣味が演劇の方。近くの病院に勤務する医師で、過去のSPACの公演に(なぜか)出てしまった方。浜本医院の患者さんで、朗読を趣味にしている方。浜本医院に通っている患者さんの家族で、SPACの企画に参加したことがある方。つまり、医療関係者や患者と、演劇や芸能に興味を持つ人たちが、はっきりと重なり合っていた。医療のシステムと演劇や文化のシステムが重なり合っていることが、今回の企画の背後にあったのだろう。
参加者の手元に台本が配られる。岩波文庫でも読める鈴木 力衛 訳から編成したものである。奥野さんがト書きを読み、面白い解説を入れながら、順番に、1ページくらいずつ台詞を読んでいく。そこに台本とは関係ない雑談も入ってきて、患者さんの診療の話になったり、共通の知り合いの医師の話になったりした。初めて会った人たちが多かったはずなのに、会話を引き出して自分の話をする動きがあった。私にとっても、そのような場に身を置くことは、とても楽しいものだった。
浜本医院に、訳書を待合室に置いてくださいとお願いしたので、私も少し自分のことを話す機会があった。「医学史と社会の対話」の夏の企画で、2017年の9月16日に松沢病院で行う「ロビーコンサート」のことを話しておいた。(この言葉は、奥野さんに教えてもらったものである)。その企画に向けて、今回のリーディング・カフェの参加は、大きなヒントになった。医療が作る共同体に文化を入れること。文化の中に、医療と身体の話題を入れていくこと。その双方向性を持つ動きを念頭に置くと、夏の企画にもプラスになるだろうし、研究者が歴史を観るときにも新しい風景が見えてくるのだろう。
SPACの『病は気から』のリーディング・カフェの情報はこちら>>

舞台公演の情報はこちら>>
SPACは静岡県が設立した劇団であり、創造的な舞台芸術活動を地元に根付かせながら、世界的な視点を持っている。日本ではなかなか見られない地方自治と芸術の関係をキープしている。1995年の設立時の初代の芸術総監督は鈴木 忠志であり、2007年からは宮城 聰が二代目の芸術総監督をつとめている。静岡はもちろん、国際的な演劇祭などでも活躍しており、地元の人々に深く愛されている。
「リーディング・カフェ」というのは、SPAC俳優の奥野 晃士いわく、(おそらく)彼が考えついたアイデアとのこと。俳優たちが一緒に台本を読む「読み合わせ」と同じように、一般参加者が和気あいあいと楽しく台本を読むのである。2008年から400回ほど行っている。今回のリーディング・カフェも楽しくて、読み方を間違えたり、難しい外国人の名前(「ディアフォワリュスさん」)がすらすらと読めなくても、怒った演出家にタバコの灰皿を投げつけられるようなことはない(笑)。
今回の企画の特に面白いところは、本物の病院で、医療にかかわる芝居の読み合わせをするところである。参加者の一人は「洒落がわかる」企画だと感心していた。モリエールの『病は気からLe Malade imaginaire 』は、1673年2月にパリで初演された作品。主演俳優はモリエールその人だったが、公演中に病で死亡するというダークなエピソードもついている。本作で特に重要なことは、当時の医師や患者を嘲笑した点である。医師たちはギリシア語とラテン語のテキストを読み解くばかりで、現実の病気や治療にはまったく疎い愚かな人々である。患者はさらに愚かで、医者たちに言われるがままに自分を病気だと思い込み、治療を受け、養生をして、薬を買い、浣腸をされている。医者を尊敬するあまり、医者の息子に自分の娘を嫁がせようとしている。そんな愚かな医者と愚かな患者が作る状況の中で、患者の弟と女中が一計を講じ、最後には娘と彼女の恋人が勝利する喜劇を描いたのが『病は気から』である。医療をたたえたり、患者に共感したりする定番ストーリーの真逆のシナリオである。
ところが、意外なことに、この作品の読み合わせに集まり楽しんでいた参加者の多くは医療関係者であった。参加者は男6名、女14名の計20名。SPACが培ってきた静岡の演劇や舞台の愛好者と、リーディング・カフェの場所を提供した浜本医院が軸になって作る医療関係者の二つの系列があった。そして面白いことに、この二つのグループは重なっていた。浜本医院に勤務する医師で、趣味が演劇の方。近くの病院に勤務する医師で、過去のSPACの公演に(なぜか)出てしまった方。浜本医院の患者さんで、朗読を趣味にしている方。浜本医院に通っている患者さんの家族で、SPACの企画に参加したことがある方。つまり、医療関係者や患者と、演劇や芸能に興味を持つ人たちが、はっきりと重なり合っていた。医療のシステムと演劇や文化のシステムが重なり合っていることが、今回の企画の背後にあったのだろう。
参加者の手元に台本が配られる。岩波文庫でも読める鈴木 力衛 訳から編成したものである。奥野さんがト書きを読み、面白い解説を入れながら、順番に、1ページくらいずつ台詞を読んでいく。そこに台本とは関係ない雑談も入ってきて、患者さんの診療の話になったり、共通の知り合いの医師の話になったりした。初めて会った人たちが多かったはずなのに、会話を引き出して自分の話をする動きがあった。私にとっても、そのような場に身を置くことは、とても楽しいものだった。
浜本医院に、訳書を待合室に置いてくださいとお願いしたので、私も少し自分のことを話す機会があった。「医学史と社会の対話」の夏の企画で、2017年の9月16日に松沢病院で行う「ロビーコンサート」のことを話しておいた。(この言葉は、奥野さんに教えてもらったものである)。その企画に向けて、今回のリーディング・カフェの参加は、大きなヒントになった。医療が作る共同体に文化を入れること。文化の中に、医療と身体の話題を入れていくこと。その双方向性を持つ動きを念頭に置くと、夏の企画にもプラスになるだろうし、研究者が歴史を観るときにも新しい風景が見えてくるのだろう。
SPACの『病は気から』のリーディング・カフェの情報はこちら>>

舞台公演の情報はこちら>>