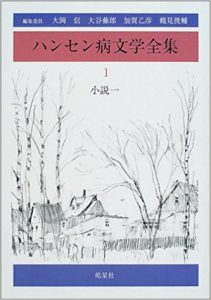企画展レポート1- 「ハンセン病と文学展」読書会の記録 /星名 宏修(一橋大学)

「ハンセン病と文学展」読書会の様子(2017年10月22日)
写真提供/上毛新聞社文化生活部(
10月22日(日)の午後1時から、草津町役場の研修室でハンセン病文学の読書会が開かれました。超大型の台風21号が接近するあいにくの天気でしたが、12名が参加しました。今回取りあげたのは、国立療養所栗生楽泉園に入所していた沢田五郎さんの小説「泥えびす」 (『ハンセン病文学全集』第1巻、皓星社、2002年)です。
1930年生まれの沢田さんは、10歳で発病し翌年に楽泉園に入所しました。ちなみに沢田さんが亡くなったのは、こ
1942年の夏、楽泉園に設置された「特別病室」という名の重監房に10ヵ月も収容された「泥えびす」が、仮死状態で「私」の部屋に移されてくる場面から小説は始まります。戦争中のさまざまなエピソードが綴られたあと、1947年の楽泉園での人権闘争を描いた場面が小説の山場となります。普段は温厚な「泥えびす」が、「特別病室」の非人道性を激烈に告発(その姿は、ふだんの「えびす」ではなく「阿修羅」に喩えられています)しますが、それと同時に患者たち自身の「心の中の悪魔」を指摘したために、療養所当局への 批判を目的とした会場の不興をかってしまうことになるのです。
その後「泥えびす」は、精神病棟に入れられてしまいます。園を脱走した罰なのか、本当に精神を病んだのかは作品には描かれていません。にわかに老けこんだ「泥えびす」は、失った家庭や「ふる里」への思いを再会した「私」に語り、その数日後に行方不明になってしまいます。小説はここで結ばれるのですが、望郷の念に駆られ故郷に帰ったものの、家族のもとには立ち寄ることができなかったことを「泥えびす」が語る場面は、感極まって号泣するという描写が、2000年代に作者の口述筆記によって加筆されたといいます。 加筆バージョンは『沢田五郎作品集 その土の上で』(皓星社、2008年)で読むことができます。
ハンセン病文学の読書会を主宰してきた佐藤健太さんによる、作者と作品についての簡潔な解説のあと読書会はスタートしました。
草津町立温泉図書館の職員で企画「ハンセン病と文学展」に関わった中沢孝之さん や、看護婦として楽泉園に長年勤務したAさんからは、この小説のリアルさが指摘され、作者の沢田五郎さんや退園したお兄さんにまつわるエピソード、さらにはご自身の楽泉園での体験がいくつも紹介されました。またご自身もハンセン病回復者で、ハンセン病文学を長期にわたって研究してきたKさんからも、この作品はノンフィクションではないかと思って著者に手紙を出したという発言がありました。少年の「私」が、「えびす」に頼まれて買った「太鼓焼き」は、実際はきんつばだったらしいというコメントなど、著者をよく知る人だからこそ可能なものだと思います。
参加者が作品を読み、それぞれの疑問や読みを出し合うなかで、3時半すぎに読書会は終了しました。あえて「正解」を求めるわけではない、各自の解釈を大切にする読書会は、私にとってとても新鮮な体験でした。
読書会が終了した後、温泉図書館で開催されている「ハンセン病と文学展」の展示と「特別病室」の歴史を伝える重監房資料館を見学して、風雨が強まるなかを東京へと向かいました。

企画展「ハンセン病と文学展」 (2017年10月21日~11月19日) ‐終了‐
■「ハンセン病と文学展」レポート特集