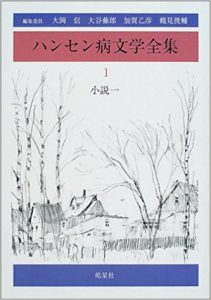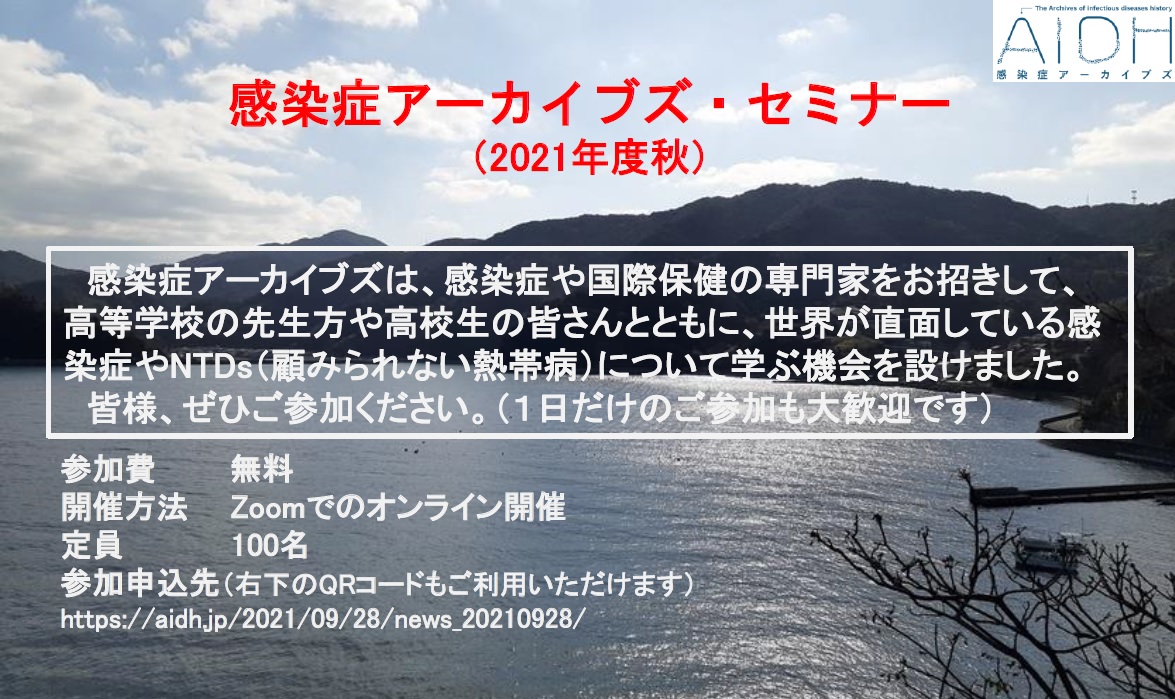企画展レポート3- ハンセン病が語られるときの揺らぎをめぐって /高林 陽展(立教大学)

頌徳公園
2017年10月21~22日、群馬県草津町にて、ハンセン病と文学展とそれに関連するフィールドワークと読書会に参加した。
わたしは医学・医療の歴史を研究している身ではあるが、このテーマに精通しているわけではない。研究の過程でいくばくかの知識はあるが、ハンセン病と文学とのかかわりはほとんど知らない。不勉強なことに、今回の読書会の課題文献として頂いた短編「泥えびす」(沢田五郎著)が最初の作品である。また、草津温泉に何度となく訪れたことはあったのだが、ハンセン病の問題を知ることはなかった。一方、全生園、駿河療養所といった国立ハンセン病療養所や国立ハンセン病資料館には見学に行ったことがある。基本的な知識はかじったことがある程度という立場で参加したことである。
ただ、参加にあたって、ある種の予感はもっていた。過去の経験から、ハンセン病というテーマは気楽に聞けるものではないと思っていたからである。実際、今回のフィールドワークで学んだことはいずれも、歴史の重みを強く感じさせるものだった。湯治のため滞在していた旅館に宿泊費が払えなくなったハンセン病者が投げ入れられたという坂を歩き、明治から昭和にかけて1,000人を超えるハンセン病者が住んでいた集落の跡を眺め、かれらに寄り添おうとしたキリスト教の伝道活動、聖公会系ミッションの聖バルナバ・ミッションについて話を聞いた。このミッションで中心的な役割をはたした女性伝道師コーンウォール・リーを記念した「リーかあさま記念館」の展示も観ることができた。そこでは、かれらの「救らい」活動が近代日本において困難さに満ちていたことが伝わってくる。多少語弊はあるだろうが、そこまでは想定内とも言える。

草津聖バルナバ教会・リーかあさま記念館
そのようなフィールドワークのさなか、いささか想定外のことに出くわした。フィールドワークで訪れた聖バルナバ教会で、草津にある国立ハンセン病療養所栗生楽泉園の男性入所者Aさんにお話を伺ったときのことである。Aさんは、草津とハンセン病のかかわりについて話してくださった。Aさんの語りは、差別と偏見といったハンセン病が抱える困難さだけに集約されるものではなかった。
たとえば、Aさんによると、子どものころ、ハンセン病者集落の外の子どもたちとなんの問題もなく遊んでいた。集落外の子どもも通う小学校でいじめをうけた経験もなかった。その様子を見たハンセン病者の母は、「お前はバカだねぇ」とAさんに言った。その言葉はAさんの心に深くつきささったが、Aさんは、それでも偏見や差別は常にあったわけではないのと語った。1941年にハンセン病者の集落(湯ノ沢集落)が取り壊され、そこにいたハンセン病者の人たちが栗生楽泉園に移ってからも、療養所の外へ出ることもあったし、街の人たちとの交流も途切れたわけではなかった。療養所内でハンセン病者に課された様々な作業も、必ずしも強制されたわけではないとも語った。ハンセン病の問題は偏見と差別の物語には収まりきらないという、Aさんの経験ないし想いを垣間見たのである。
しかし、そこで教会の牧師である松浦さんが補足的な解説を買ってでると、場の様子は一変した。松浦さんは、一般的に言えば、差別と偏見はあったのだとフィールドワークの参加者に語った。Aさんの語りを相対化しようとしたのである。それに対して、Aさんは憤りの表情を隠さなかった。持っていた杖を教会の床につき、「そういうこともあったでしょうけどね」と言った。場に緊張がはしった瞬間だった。
しかし、よくよく考えれば、Aさんの語りの端々にも差別や偏見の問題は入り込んでいた。Aさんはハンセン病ないしハンセン病者という言葉は使わなかった。その代わりに「白い目で見られた人たち」と表現した。また、一家で軽井沢へと電車(草軽軽便鉄道)で向かおうとしたとき、おなじくハンセン病をわずらっていた父親が乗車拒否されたことも語ってくれた。そうした話からは、差別がまったくなかったわけではないことがわかる。それでもハンセン病者と草津の療養所は「常に」社会から隔絶されたわけではないと語り、松浦さんの言葉には容易には同意しなかった。緊張感のある揺らぎ、ハンセン病をめぐる語りの揺らぎがそこにはあった。ハンセン病を生きた経験、そしてそれを意味づけようとする営み。そのふたつがハンセン病を語ることを揺らがせる。その揺らぎは重く、そうそう受け止めきれるものではない。率直に言って、わたしは身じろいだ。
フィールドワークを終えた夜、主催者の一人であるハンセン病文学編集者の佐藤さんたちと夕食をともにした。そこに、一緒にフィールドワークに参加した初老の男性Bさんがいた。Bさんはハンセン病文学に興味があり、一連のイベントに参加したのだと自己紹介をしてくださった。しかし、彼の口から語られる話はどこか療養所との深いつながりを感じさせた。ただ、Aさんがハンセン病という言葉を使わず「白い目で見られた人たち」と表現していたことも頭をよぎり、聞くに聞けなかった。すると、気を使ってくださったのか、10代のころに熊本の国立ハンセン病療養所菊池恵楓園にいらっしゃったこと、特効薬プロミンによって回復なさり療養所から逃げ出したこと、その後は療養所の外で職を得て奥さん・お子さんとの生活を営まれていることを話してくださった。
印象的だったのは、療養所から出た後は、とにかくハンセン病のことは目にしないように暮らしたとおっしゃったことである。たまたま買った本にハンセン病のことが書いてあると、すぐに捨てたそうである。ただ、お子さんが成人したころから、自分の人生とは何だったのかを問うようになり、ハンセン病文学を読むようになった。ハンセン病とは、療養所とは、いったいなんだったのか。そう問いながら、ハンセン病者の文学作品を読むのだとBさんは言う。ここにもハンセン病をめぐる語りの揺らぎがある。ハンセン病のことを語らない、かかわらないように生きてきたBさんがいま一度立ちどまり、ハンセン病と向き合い語る。避けることと向き合うことのあいだの揺らぎである。
このような揺らぎは、フィールドワークの翌日に開かれた読書会でも見られた。そのことに触れる前に、読書会でとりあげられた作品である沢田五郎の短編「泥えびす」について説明しておこう。「泥えびす」のあらすじは以下の通り。主人公は、楽泉園に入所していた少年。彼の視点を通じて、ある男の物語が描き出される。その男は、楽泉園に着くと早々に重監房へと入れられた男性のハンセン病者である(重監房については後述)。重監房から出たあと、彼は笑顔を絶やさず、穏やかで目立たぬようふるまう。また、彼はくず鉄拾いに精を出し、常に泥にまみれていた。そのことから「泥えびす」なるあだ名がつく。その彼は、戦後直後に行われた人権運動の盛り上がりのなか開かれた療養所の職員たちを糾弾する集会で、声を荒げて重監房の悲惨さを告発する。笑顔を絶やさない彼が豹変したことに、語り手の少年を含め周囲は驚いた。その後、泥えびすは、療養所に居心地の悪さを感じ、療養所を逃げ出す。そして、家族のもとに帰ろうとする。しかし、ハンセン病をわずらったわが身を思い、家を遠目で見るだけで帰還をあきらめた。そこで、もはや戻るべき場所はないのだと療養所に戻るのだが、逃走に対する懲罰のため精神病棟なる独房のような部屋に入れられてしまう。しかしある日、そこから忽然と姿を消し、そのまま行方知らずとなる。最後に、語り手の少年は「泥えびす帰ってこい」と叫ぼうとするもやめてしまう。ハンセン病を生きることの酷薄さを知ってのことである。
Bさんは、この作品には自身にとって示唆的な場面があると語った。それは、泥えびすが、ヘビに半身を飲み込まれたカエルという暗喩を語る場面である。半身を飲み込まれたカエルは完全に捕らえられたわけではない。なんとか逃げようともがき、前に進もうとする。しかしほとんど進むことはできず、いつか完全に飲み込まれてしまう可能性も残されている。ここでのヘビはハンセン病、カエルはハンセン病者である。ハンセン病という運命に飲み込まれつつも、完全に取り込まれる恐れを抱きつつも、もがき動くハンセン病者。ハンセン病という運命の暴力性が強く印象づけられる場面である。Bさんは、この部分が自身の経験と重なるのだと言う。かつて忘れようとしたハンセン病はヘビであり、Bさんにいまだ噛みついたまま、ということだろうか。ハンセン病はそれほどまでに、人間のアイデンティティを引き裂くものだったのだろう。
フィールドワークの翌日。午後の読書会の前に栗生楽泉園を訪れた。目的は、園内にある重監房資料館を訪問すること。重監房とは、戦前に全国のハンセン病療養所のなかでも、楽泉園だけに設けられた懲罰的な獄舎のことである。草津に限らず、全国の療養所で当局に逆らった人たちが裁判もなく収容された獄舎である。資料館ではまず、この重監房の問題を告発するうえで重要な役割を果たした、栗生楽泉園の入所者谺雄二さんの一生を振り返る映像を観た。谺さんの人生、重監房問題の告発から重監房資料館の開設にいたるまでの闘争の経過をたどったものである。
その後、資料館の展示を見た。展示のメインは、当時の重監房を再現したものである。5メートル以上はあろうかというモルタルの壁に4畳半ほどの独房。その入口は小さく、かがまねば入れない。独房には、横1メートル・縦15センチほどの換気口と食事を入れるための穴があいているだけである。光はほとんど入らず、食事も1日に2度わずかなものしか供されなかった。冬の寒い日はマイナス17度にもなるという草津の地のことである。獄死する者が相次いだのも当然の結果だった。こうでもして守られたもの、守られた秩序とは何だったのか。人が人に為すことの極限はここにあるのではないか。そう考えたとき、ある種、揺らぎのない思いがあらわれた。
しかし、そこでAさんとBさんの言葉を思い返した。人権侵害、差別、告発、闘いの歴史を語ることは、ハンセン病の語りの中心にあるものだろう。揺らぎのない、確固とした語りがそこにはある。わたしも、その語りを共有することに違和感はない。しかし、AさんとBさんの語りにみた揺らぎもまた、ハンセン病の歴史そのものではないだろうか。ハンセン病というヘビに半身を飲み込まれ、それでも這いずって動くカエル。カエルは、ときに運命に対して呪詛の言葉を吐き、あるいはつらい運命を忘却しようという努力にいそしみ、もしくは過去の善き経験を抱擁してみようとする。そのすべてがあってこその歴史なのだろう。
そうした複雑に絡み合う語りを、「ヘビ」どころか「蚊」に咬まれた程度の生しかおくっていない者でも、受けとめられるだろうか。そもそも受けとめようとしてもいいのだろうか。ハンセン病の過去をめぐる語り、その揺らぎをどう受けとめるのか。容易ならざる問いを得た、というのが率直なところである。

企画展「ハンセン病と文学展」 (2017年10月21日~11月19日) ‐終了‐
■「ハンセン病と文学展」レポート特集